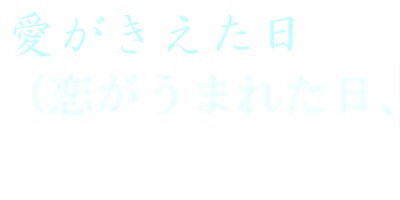愛がきえた日
静雄はふざけるなと憤ったし、実際そういった意味の罵声も浴びせ続けた。性質の悪い嫌がらせならもう慣れたが、それにしたってこれは質が悪すぎる。冗談言うな、そう怒鳴れば臨也は例のにやついた笑みでこう返すのだ。
「本気なのに信じてくれないなんて酷いねぇ」
「っ…手前のそのツラでよくんな事言えるよなぁ、このノミ蟲野郎!」
頷く気には到底なれなかった。臨也との不本意ながらも長い関係の中で、この男と絶対に結び付けてはいけない言葉が信頼と好意だという事を、静雄は知っていたからだ。今まで何度、ちらりとあるいは大げさに見せられた愛情じみたものに期待をし、裏切られたかわからない。
憎悪の固まりを歪に成形して、蜜のような光沢とにおいを持った愛情に見せかけるのは臨也の得意技である。近寄れば暗闇からその塊を差し出して甘く誘う。おずおずと舌を差し出した途端にその光沢は鈍く光る刃のそれとなり、静雄の脆い部分を容赦なく抉るのだった。
愛がきえた日
二度と騙されるものか、と全身に針を巡らしたように警戒心を剥き出しにしてどれだけ経った頃だろう。静雄はごろりと寝返りをうつ。
今日は仕事も無いし、どこに行こうという予定もない。久しぶりに一日怠惰に過ごそうと、布団にひっついたのは今朝の事だ。しかしうとうととまどろんでは、意識が浮上した時の自分を包む暖かさに幸せを覚えるといった行為にも2時間経てば飽きてしまった。せめて半日は怠けるのだと半ば意地になっていると、勝手に頭が記憶の巻き戻しを始めて今に至る。
そうだ確かに俺はずっと、あいつに騙されるまいとしていた、と静雄は茫洋とした目付きで昔の記憶を探る。あの決心に嘘や誤魔化しなどかけらも含まれていなかったはずなのに、そう思うと僅かに口元に笑みがたちのぼるのを隠せない。静かな、苦笑にも似た表情を浮かべたまま静雄は再び目を瞑る。
そう昔では無い思い出と共に押し寄せるのは水音だ。
あの日は雨が降っていた。鉛色に染まった陰気な街並みを、2人で縫うように駆けずり回る常の騒動の最中、静雄は臨也を追った先の路地裏で押し倒されるという失態を犯したのだ。
追いつめた所で殴りつける予定だった。臨也もそれを覚悟しているようで、生白い顔で目だけをぎらぎらと捕食者のように光らせながらナイフをこちらに向けていた。振りかぶり、音を立てて彼の顔面を殴ろうとした時、うっかり、本当にうっかり、静雄はぬかるみで足を滑らせたのである。
体勢が大きく後ろに崩れ、空いたスペースに飛び込んで来た臨也がナイフと共に腹へと降り落ちる。瞬間世界がぐるりと回り、静雄の耳には雨がコンクリートを打つ音や、互いの息といったものまで何もかもがボリュームのつまみを切ったかのように聞こえなくなった。泥水に似た色合いのもったりした雲がいっぱいに映り込み、視界の端に臨也の体と光る切尖を捉えた時、滑稽な話だが静雄はたしかに死を意識したのだ。
ところが、予想した鋭い痛みはいつまで経っても静雄を襲う事は無かった。
クレッシェンドに耳の中を浸していく雨音に混じって、カランと涼やかな金属音が聞こえた。一瞬遅れて、臨也のナイフが彼の手によって投げ捨てられたのだという事を知る。
「ほんとうは、もっと、」
臨也はそう言って、静雄に縋りつくように顔の横へと腕をついた。
世界の音を閉じ込めてしまうかのように、間断なく雨が降りしきる。降り注ぐ冷たい水滴のせいでぐっしょりと束になるまで濡れた黒髪を、彼はかきあげようともしなかった。簾のようになってしまった前髪の奥にある瞳が、ぎゅうと辛そうに細められる。
本当は。その後に続いたのであろう言葉が、彼の口から出る事は無かった。二呼吸分の荒い息が冷えた外気に溶けた後、臨也はここ2年近く使い古された台詞を吐いた。
「シズちゃん……好きだよ」
音という音を吸いこんでしまう雨の中、彼の声だけがいやにはっきりと耳を打つ。
「愛には慣れてるんだ、俺は。人間全てを愛してるからさ」
「……」
「慣れてるはずだったんだけど、でも、違ったみたい」
「…手前は俺を、殺したいんだろうが」
「うん、死んでほしい」
そこは即答するのか、とわかりきっていた答えに思わず苦笑しそうになった。しかし臨也の、今まで見た事の無い奇妙な真顔に笑うのを躊躇う。彼は静雄を見下ろしていたが、彼の瞳は静雄を通り越して、どこか違う何かを見ているような目つきをしていた。濡れそぼった前髪が邪魔をして、感情が読めない。
「けど、今じゃない。この先ずっとずっと年取って、シズちゃんが皺だらけの耄碌親父になって、ガードレール振り回す化け物だったなんて考えられないだとか言う人間も周りから少しずついなくなって、そうしたら俺が、君を」
静雄は自身の掌に爪を立て、固い拳を作る。僅かに滲む痛みを拾おうと、脳の神経を敏感に張り巡らせた。
そうでもしないと、臨也の色を失った唇からこぼれ落ちる夢物語に溺れそうだった。夢物語だと、思った。静雄にはその物騒な言葉達が、届かぬ星のかけらにも似た儚げな輝きを持っているように思えてならなかったのだ。
煙草を吸う時のように、深く息を吸う。冷涼とした空気が肺に絞るような痛みを与えてきたが、構わず限界まで吸い込んだ。
その僅かな間に己の内に潜む傷がぱっくりと瘡蓋を割り、たらりと流れ出すのを感じた。これが最後だ、口には出さず眼だけで訴える。傷が癒えるも癒えないも、互いに嫌悪の情を鎧にするのもこれが最後だ。
粘度のある感情がじわじわ心に沁み込んでは消えていくような気すら、した。
「…った」
「、え?」
何、そう戸惑い気味に問いかける臨也の、そのうざったい前髪を掴んで引き上げる。静雄の射竦めるような強い瞳の中いっぱいに、額まであらわな瞠目した間抜け面が映り込んだ。
「わかったっつってんだよ…!」
本当は、と臨也は言った。あの瞬間、臨也の言おうとしていた事は恐らく誰にも知られたく無いとひた隠していた事のように思えた。少なくとも嘘では無い。
腹を括ったのだ。自身の血管や臓器の更に内側で、何年も凝固もせずにたゆたっていた感情を受け入れる覚悟を、静雄は僅か一息の間に決めた。期待をしては裏切られた、その期待に込められた自分の心に名づける名称が何であるかを今、知った。
彼がかつて一度も漏らした事の無い本音を、ぶちまけようとしてまで静雄に伝えたい事がその、好意だと言うのなら。信じてもいい、そう思ってしまった。
「…ばかなシズちゃん」
「いざ、」
彼の告白に返す類の言葉は、了承なんかではなくて他にあると知っていた。それでも臨也が、静雄にその言葉を求める事は無かった。ただ一言、同じ言葉を二回、呟いた。
「……ばかだね、ほんとに」
あの日の臨也の顔は一生忘れない、と静雄は反芻する。忘れてやるものか、事ある毎に思い出しては笑ってやる。事実今、静雄の笑顔は大変に意地の悪いものであろうというのも自覚していた。
つらそうに眇めた瞳を目一杯見開き、その後臨也は、笑ったのだった。顔じゅうをくしゃりと歪めるように、眉間にしわを寄せながらも眉尻を下げるという奇妙この上無い表情で。
小さい窓から弱い陽光が差し込んできた。そろそろ昼時なのかもしれない。
外に出れば凍てつく寒さな事には間違いないけれど、室内にいる限りは熱だけを与えてくるその光から逃げるように静雄は身を捩る。思えば、あの雨の日以来臨也と顔を合わせていなかった。もう1週間ほど経つはずだ。
もう少し、この狭い部屋で平穏を貪ったら池袋の街をふらつこうか。そんな事を考える。新宿に行こうとは不思議と思わなかった。会うなら会う、会わないならそれはそれでいい。そう思っていたというのもあるし、なぜか今日、臨也も池袋にいるような気がした。
とりあえず。とりあえずだ、太腿あたりでもこもことわだかまっていた毛布を口元まで引き上げながら静雄はそう呟く。後少しだけ寝てしまおう。考えるのも動くのも、その後でいい。
ばか、と笑った臨也と再び対面した時、何と言えばこないだのような情けない顔をするだろうと想像しながらまどろむのは愉快だった。答えの出ない問いが段々と輪郭を失い、静雄は穏やかな小舟に揺られるような眠気に飲み込まれていく。咎める者は誰もいない、何せ今日はせっかくの休日である。
ゆったりと呼吸を繰り返す静雄を冬の太陽が照らし出す。傷んだ金髪が、光の粒を潜ませているかのようにきらめいた。